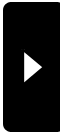2007年10月30日
スポチャン少年少女大会
栗東市でスポーツチャンバラ少年少女大会を開催。
http://www.shiga-spochan.net/
栗東市民体育館には、役員と選手併せて70名が参加。草津・栗東の会員や県下の湖南市、菩提寺、甲賀・水口町、日野町からも参加し。
種目は、小太刀、長剣、二刀、支部対抗の団体戦(3人制)とあり、幼児から小学生、中学生以上、女子の部に分かれて対戦。

道衣の帯は、級位・段位に応じて変わり、10級位~1級の級位(白・紺・緑・赤・茶色等)と初段からの黒帯になります。
身体の主要部位に打ち込めば1本で、2本目は有りません。どこに当たっても怪我を負うからです。また、相打ちは両者負け。
小太刀の部は基本で元々の小太刀護身道からのもので、なるべく年齢等に応じて対戦する様にしています。
幼児の部、小学12年、34年、56年、中学以上、女子の部。

この後、近畿大会が大阪府門真市のなみはやドームで12月2日に開催。また、平成20年には滋賀県で第21回全国スポレク祭が開催されることから、協賛事業で参画予定。会員一同頑張っています。随時見学、体験は大歓迎です。

http://www.shiga-spochan.net/
栗東市民体育館には、役員と選手併せて70名が参加。草津・栗東の会員や県下の湖南市、菩提寺、甲賀・水口町、日野町からも参加し。
種目は、小太刀、長剣、二刀、支部対抗の団体戦(3人制)とあり、幼児から小学生、中学生以上、女子の部に分かれて対戦。

道衣の帯は、級位・段位に応じて変わり、10級位~1級の級位(白・紺・緑・赤・茶色等)と初段からの黒帯になります。
身体の主要部位に打ち込めば1本で、2本目は有りません。どこに当たっても怪我を負うからです。また、相打ちは両者負け。
小太刀の部は基本で元々の小太刀護身道からのもので、なるべく年齢等に応じて対戦する様にしています。
幼児の部、小学12年、34年、56年、中学以上、女子の部。

この後、近畿大会が大阪府門真市のなみはやドームで12月2日に開催。また、平成20年には滋賀県で第21回全国スポレク祭が開催されることから、協賛事業で参画予定。会員一同頑張っています。随時見学、体験は大歓迎です。

2007年10月25日
沖縄より、戦後史雑感
沖縄の友人からのメールがあって、その後書棚をのぞき込んでいたら
私なりの「沖縄関係図書」を選んでみた。
沖縄に根付く問題、第一尚王朝、第二尚王朝から沖縄県設置、大東亜戦争、沖縄県祖国復帰と延々に歴史的に辛い立場にあったからこそ「沖縄独立論」が続いている。1997年に発行された「沖縄独立宣言」は、大山朝常先生の著書。
元沖縄市長=以前のコザ市長である。続編を書こうとしているさなか逝去された。
 著書の左下は、大山先生の名刺。2~3度お会いしたが最後は、新大阪駅近くのホテルロビーでお茶をごちそうになつた。その優しい笑みに、仏様の様な感慨を受けた。
著書の左下は、大山先生の名刺。2~3度お会いしたが最後は、新大阪駅近くのホテルロビーでお茶をごちそうになつた。その優しい笑みに、仏様の様な感慨を受けた。
現在の沖縄市、当時のコザ市長を4期16年勤められている。特に1970年のコザ騒動の時や安保騒動、祖国復帰問題に活躍されてきたことから、その苦労を言葉にあらわせないものだと思う。
政治的な立場からすれば当然にその著書を書き残されたのだとーー
 「南方同胞援護会17年のあゆみ」は、(財)沖縄協会の戦後の復帰までの活動の歴史である。1975年~6年頃にお会いしたが
「南方同胞援護会17年のあゆみ」は、(財)沖縄協会の戦後の復帰までの活動の歴史である。1975年~6年頃にお会いしたが
当時の協会専務理事の吉田嗣延先生等が中心となり戦後の苦節
を乗り越えられて残された活動報告である。
当時は、「南方同胞援護会」と称していた中、後、(財)沖縄協会となっている。
戦後の同胞達の援護から、復帰前の沖縄との折衝、復帰に至る
経緯等があらわされ苦節が忍ばれる。
沖縄について、専門的に学んだわけでもなく雑学だけであるが、ただ、学生時代の延長に生きている人間として当時の人生観がつきまとっていることは確かである。
その中で、選んでみただけである。
一方で、「沖縄学の父」と呼ばれた伊波晋猷の「古琉球」(岩波文庫)等に視点を移すと、文学的な見地からの本土との共通点が多々あり無関心ではいられなくなる。
沖縄の万葉集と言われた「おもろそうし」(難しくて)、天孫降臨にまつわる「久高島のイザイホー」、馬琴や三島由紀夫の「椿説弓張月」、言語学からくる母音の変遷。
食の文化、酒=泡盛の文化。
私なりの「沖縄関係図書」を選んでみた。
沖縄に根付く問題、第一尚王朝、第二尚王朝から沖縄県設置、大東亜戦争、沖縄県祖国復帰と延々に歴史的に辛い立場にあったからこそ「沖縄独立論」が続いている。1997年に発行された「沖縄独立宣言」は、大山朝常先生の著書。
元沖縄市長=以前のコザ市長である。続編を書こうとしているさなか逝去された。
 著書の左下は、大山先生の名刺。2~3度お会いしたが最後は、新大阪駅近くのホテルロビーでお茶をごちそうになつた。その優しい笑みに、仏様の様な感慨を受けた。
著書の左下は、大山先生の名刺。2~3度お会いしたが最後は、新大阪駅近くのホテルロビーでお茶をごちそうになつた。その優しい笑みに、仏様の様な感慨を受けた。現在の沖縄市、当時のコザ市長を4期16年勤められている。特に1970年のコザ騒動の時や安保騒動、祖国復帰問題に活躍されてきたことから、その苦労を言葉にあらわせないものだと思う。
政治的な立場からすれば当然にその著書を書き残されたのだとーー
 「南方同胞援護会17年のあゆみ」は、(財)沖縄協会の戦後の復帰までの活動の歴史である。1975年~6年頃にお会いしたが
「南方同胞援護会17年のあゆみ」は、(財)沖縄協会の戦後の復帰までの活動の歴史である。1975年~6年頃にお会いしたが当時の協会専務理事の吉田嗣延先生等が中心となり戦後の苦節
を乗り越えられて残された活動報告である。
当時は、「南方同胞援護会」と称していた中、後、(財)沖縄協会となっている。
戦後の同胞達の援護から、復帰前の沖縄との折衝、復帰に至る
経緯等があらわされ苦節が忍ばれる。
沖縄について、専門的に学んだわけでもなく雑学だけであるが、ただ、学生時代の延長に生きている人間として当時の人生観がつきまとっていることは確かである。
その中で、選んでみただけである。
一方で、「沖縄学の父」と呼ばれた伊波晋猷の「古琉球」(岩波文庫)等に視点を移すと、文学的な見地からの本土との共通点が多々あり無関心ではいられなくなる。
沖縄の万葉集と言われた「おもろそうし」(難しくて)、天孫降臨にまつわる「久高島のイザイホー」、馬琴や三島由紀夫の「椿説弓張月」、言語学からくる母音の変遷。
食の文化、酒=泡盛の文化。
2007年10月22日
スポーツチャンバラ親善大会
スポーツチャンバラ
http://www.shiga-spochan.net/
得物は空気を注入したエアー剣を使用するためで軽くて安全です。
来年の全国スポレク祭が滋賀県で開催されますが、滋賀県スポーツチャンバラ協会も協賛事業として参加予定で準備を進めています。

10月20日はレクリエーション協会主催の大会で、スポーツチャンバラ協会も親睦大会を開催。
幼年・小学低学年・高学年中1・一般の部に分かれて熱戦。
野洲市総合体育館には、各種スポーツの試合も開催されていたので、途中、体験コーナーも行いました。
老若男女に関係なくスポチャン教室を開きました。
10月28日は栗東市少年少女大会を開催(栗東市民体育館)
http://www.shiga-spochan.net/
得物は空気を注入したエアー剣を使用するためで軽くて安全です。
来年の全国スポレク祭が滋賀県で開催されますが、滋賀県スポーツチャンバラ協会も協賛事業として参加予定で準備を進めています。


10月20日はレクリエーション協会主催の大会で、スポーツチャンバラ協会も親睦大会を開催。
幼年・小学低学年・高学年中1・一般の部に分かれて熱戦。
野洲市総合体育館には、各種スポーツの試合も開催されていたので、途中、体験コーナーも行いました。
老若男女に関係なくスポチャン教室を開きました。
10月28日は栗東市少年少女大会を開催(栗東市民体育館)
2007年10月18日
古酒・泡盛
 古酒・泡盛
古酒・泡盛昨日は、休日だったので、久しぶりに「泡盛」を試飲。
前回、試飲したのは、4月でした。通常、3年以上ねかすと良いらしいですが。我が家の泡盛は、平成12年4月に仕入れたもの。と言っても、5升瓶に泡盛「満座」を5升+2合を当地でで購入し、自宅で仕込んだものです。
満座は、恩納酒造のものですが、購入先の仲里さんに講義を受けてねかせています。
本来は、瓶を3~5本くらい用意して順番に仕次を繰り返し、本瓶に保存するらしいですが。我が家は一瓶です。
「3瓶・試飲・仕次→2瓶・試飲・仕次→本瓶・試飲・仕次」といった具合です。
ねかす程に、瓶との相性がよくなるとのこと。
瓶は、沖縄の土か、昔は沖縄から職人が派遣されて制作していたベトナム産の土瓶らしい。
まろやかな古酒・泡盛をちびりチビリと飲むことに---
2007年10月15日
沖縄より
沖縄についての感想ありがうございます。
島田知事については、「島守人」としての慰霊塔が摩文仁ケ丘に建立されています。
最期は、摩文仁の東方か喜屋武岬の洞窟だともいわれ確証が有りません。
沖縄戦については、当初32軍が編成されたときには、陸軍と海軍根拠隊が県民共々に陣地構築にあたっていました。
しかしながら、19年10月頃から現地の実情を考慮せずに大本営や参謀本部が編成替えをした為に混乱を来たせました。
守備軍の減少は現地を不安に陥れたと考えられます。特に、金沢9師団や後の熊本6師団抽出が傷手でした。本土決戦の前哨戦は沖縄か、台湾か、比島かといったところで判断を誤ったと思います。
海軍根拠隊だけが減少しながらも現地の県民共々に構築したいみたいです。
32軍の牛島司令官、長参謀長以下、62師団藤岡中将、24師団雨宮中将、海軍根拠隊太田少将等が中心となっています。
牛島中将の最期は摩文仁、太田中将は豊見城小禄、藤岡中将は摩文仁、雨宮中将が糸満宇江城等です。
以下、現地前線部隊と県民、ひめゆり部隊、鉄血勤皇隊等との間に混乱を生じ、軍が最優先となったところと、最後まで県民を守ったところがあったことと考えられます。
島田知事については、「島守人」としての慰霊塔が摩文仁ケ丘に建立されています。
最期は、摩文仁の東方か喜屋武岬の洞窟だともいわれ確証が有りません。
沖縄戦については、当初32軍が編成されたときには、陸軍と海軍根拠隊が県民共々に陣地構築にあたっていました。
しかしながら、19年10月頃から現地の実情を考慮せずに大本営や参謀本部が編成替えをした為に混乱を来たせました。
守備軍の減少は現地を不安に陥れたと考えられます。特に、金沢9師団や後の熊本6師団抽出が傷手でした。本土決戦の前哨戦は沖縄か、台湾か、比島かといったところで判断を誤ったと思います。
海軍根拠隊だけが減少しながらも現地の県民共々に構築したいみたいです。
32軍の牛島司令官、長参謀長以下、62師団藤岡中将、24師団雨宮中将、海軍根拠隊太田少将等が中心となっています。
牛島中将の最期は摩文仁、太田中将は豊見城小禄、藤岡中将は摩文仁、雨宮中将が糸満宇江城等です。
以下、現地前線部隊と県民、ひめゆり部隊、鉄血勤皇隊等との間に混乱を生じ、軍が最優先となったところと、最後まで県民を守ったところがあったことと考えられます。