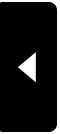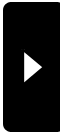2009年09月21日
家庭菜園・水やり
畝らしく
漸く、畝らしくなりました。石灰や肥料を散布した後、攪拌し「種まき」終了。

手前が「大根」、真ん中が「にんじん」。「にんじん」の畝には、水分の蒸発
防止の為に枯れ葉を散らしておきました。
近くの菜園を見学すると、「籾殻」を蒔くそうですが、無かったために代用です。
後は、保護シートの準備。
ついでに、畝を割って、肥料代わりに枯れ葉を埋めました。
近所のおじさんに教えてもらった知恵ですがーー。

奥の畝は、あたらに石灰を蒔いたところです。暫くねかします。
漸く、畝らしくなりました。石灰や肥料を散布した後、攪拌し「種まき」終了。
手前が「大根」、真ん中が「にんじん」。「にんじん」の畝には、水分の蒸発
防止の為に枯れ葉を散らしておきました。
近くの菜園を見学すると、「籾殻」を蒔くそうですが、無かったために代用です。
後は、保護シートの準備。
ついでに、畝を割って、肥料代わりに枯れ葉を埋めました。
近所のおじさんに教えてもらった知恵ですがーー。
奥の畝は、あたらに石灰を蒔いたところです。暫くねかします。
2009年09月14日
家庭菜園、畝づくり
「家庭菜園」のまねごとスタート
漸く、草刈りの終わった畑です。形になってきました。

盆休みの5日間、朝夕に背丈ほどに伸びていた雑草刈りが終わり、
除草したところで、畝の形が出来上がり。
まず、形からと云うことで、道具をそろえて作業。

ヤブ蚊の大群におそわれつつ、作業をしていました。
こう云う時には、「虫除けスプレー」、「腰への携帯用(扇風機形)」が
必需品でした。
「石灰散布」

その後、石灰を散布して攪拌しました。
酸性土壌を改良する為には石灰等が事が必要とのことで、まずは
この程度のスタートです。(但し、野菜によりけりで要・注意)
秋の作付けにはどのような野菜か、肥料は何かとDIYで検討中。
細君は、情報集め、亭主は力仕事。
未だ、ここまでで、かっこいい畝にはほど遠く、笑われますが、失敗を繰り返しながらも
形作って行こうと張り切っています。
1週間~10日ほどで、秋野菜の作付けにチャレンジ。(^o^*)
漸く、草刈りの終わった畑です。形になってきました。
盆休みの5日間、朝夕に背丈ほどに伸びていた雑草刈りが終わり、
除草したところで、畝の形が出来上がり。
まず、形からと云うことで、道具をそろえて作業。
ヤブ蚊の大群におそわれつつ、作業をしていました。
こう云う時には、「虫除けスプレー」、「腰への携帯用(扇風機形)」が
必需品でした。
「石灰散布」
その後、石灰を散布して攪拌しました。
酸性土壌を改良する為には石灰等が事が必要とのことで、まずは
この程度のスタートです。(但し、野菜によりけりで要・注意)
秋の作付けにはどのような野菜か、肥料は何かとDIYで検討中。
細君は、情報集め、亭主は力仕事。
未だ、ここまでで、かっこいい畝にはほど遠く、笑われますが、失敗を繰り返しながらも
形作って行こうと張り切っています。
1週間~10日ほどで、秋野菜の作付けにチャレンジ。(^o^*)
2009年07月21日
ウェストン・天竜川
ウオルター・ウエストン

天竜川の時又港に石碑が建つ。
船下りは「弁天港」から乗船し「時又港」下船。30分~40分の船旅。
京都の「保津川」船下りより短いですが。
ウオルター・ウエストンと云えば、日本アルプスを世界に紹介したイギリスの登山家。
牧師でありながら、登山家でもあった彼は、日本の秀麗な山々を世界に紹介したことで
有名です。その名も日本アルプス。北・中央・南アルプス。
ウエストンのレリーフは、上高地の梓川の測道岸壁にはめ込まれているますが、
ここ、天竜川にもあったとは感激でした。
上高地と云えば、穂高山脈、焼岳、大正池、梓川等々の情景が浮かびます。
ウエストンは、ここ天竜川の船下りをも紹介したそうで、その石碑が時又港に建立されています。
4月には「天竜川ウエストン祭」、6月には「上高地ウエストン祭」が開催れます。

天候もよく、青空の下に颯爽と舵を取る船頭さん。
天竜川の時又港に石碑が建つ。
船下りは「弁天港」から乗船し「時又港」下船。30分~40分の船旅。
京都の「保津川」船下りより短いですが。
ウオルター・ウエストンと云えば、日本アルプスを世界に紹介したイギリスの登山家。
牧師でありながら、登山家でもあった彼は、日本の秀麗な山々を世界に紹介したことで
有名です。その名も日本アルプス。北・中央・南アルプス。
ウエストンのレリーフは、上高地の梓川の測道岸壁にはめ込まれているますが、
ここ、天竜川にもあったとは感激でした。
上高地と云えば、穂高山脈、焼岳、大正池、梓川等々の情景が浮かびます。
ウエストンは、ここ天竜川の船下りをも紹介したそうで、その石碑が時又港に建立されています。
4月には「天竜川ウエストン祭」、6月には「上高地ウエストン祭」が開催れます。
天候もよく、青空の下に颯爽と舵を取る船頭さん。
2009年07月20日
馬篭宿・中山道
中山道「馬篭宿」
業界の先進地視察で、中部電力・川越発電所を訪問。
川越火力発電所では、燃料にLNG(液化天然ガス)を使用している。
発電所の3号・4号系列はガスタービンと蒸気タービンを組み合わせた
1300度C級コンバインドサイクル発電と云う新しい発電方式…??…??
解説を中止します。ややこしいし、理解してません。
本題に移ります。
中山道・馬篭の枡形辻。

道幅の狭い石畳の街道沿いにせせらぎが…。
川上から流れた水を取り入れ水車(右端奥)に利用。

馬篭宿の建物は、明治28年と大正4年の大火で全焼したらしく
現在の建物は、戦後の「まちづくり」の一環で再現したとのこと。

整備された石畳。本来は、石畳ではない為に、雨が降ると
ぬかるみ大変だったそうである。
江戸時代の記録では、馬篭の街道は三町三十間(約400m)
だったらしく、この狭い街道沿いに本陣、脇本陣、問屋、旅籠があり、
物資を運んだ人々、京や江戸を目指す庶民、大名行列で混雑していたと云う。
業界の先進地視察で、中部電力・川越発電所を訪問。
川越火力発電所では、燃料にLNG(液化天然ガス)を使用している。
発電所の3号・4号系列はガスタービンと蒸気タービンを組み合わせた
1300度C級コンバインドサイクル発電と云う新しい発電方式…??…??
解説を中止します。ややこしいし、理解してません。
本題に移ります。
中山道・馬篭の枡形辻。
道幅の狭い石畳の街道沿いにせせらぎが…。
川上から流れた水を取り入れ水車(右端奥)に利用。
馬篭宿の建物は、明治28年と大正4年の大火で全焼したらしく
現在の建物は、戦後の「まちづくり」の一環で再現したとのこと。
整備された石畳。本来は、石畳ではない為に、雨が降ると
ぬかるみ大変だったそうである。
江戸時代の記録では、馬篭の街道は三町三十間(約400m)
だったらしく、この狭い街道沿いに本陣、脇本陣、問屋、旅籠があり、
物資を運んだ人々、京や江戸を目指す庶民、大名行列で混雑していたと云う。
2009年07月19日
馬篭宿・「夜明け前」藤村
中山道・馬篭宿

中山道・江戸へ八十里・京へ五十二里
中山道は、69宿場からなりたっており、江戸から妻篭宿を過ぎ
馬篭峠(標高800m余り)を超えると馬篭宿である。
同じ中山道11宿の中、奈良井宿は峠を過ぎると平坦な街並みとなるが
馬篭は山中の登り坂で険しい。しかしながら、江戸と京を結ぶ要衝である為に
人と物資の行き来で繁栄を極めたと云う。
ここに、本陣、脇本陣、旅籠や物資集積所があつた。
島崎藤村・「夜明け前」

夜明け前・「木曽路はすべて山の中にある……」
全4冊(岩波文庫)
「藤村記念館」島崎藤村は馬篭に本陣を経営し、庄屋も勤めた
裕福な家庭に育った。
母の実家・島崎家も妻篭宿の本陣を営んでいた。
その後、東京に移り住むが、小説「夜明け前」は、父をモデルにした
とも云われている。
主人公・青山半蔵は裕福な家庭の中で父から国学の素養を学び影響を受ける。
当時の徳川・武士社会に疑念を抱き始め、社会の矛盾に対して平田学派による王政復古の
夢を見る。
幕末の動乱は明治維新となり、変革された世は王政復古で迎えられると確信しつつ、啓蒙を続ける。
しかしながら、明治維新が終われば西洋の近代化の波の中、中山道が廃止され、
新道は木曽川沿いとなり馬篭、妻篭等の宿場街は没落の一途を辿り、貧困社会をまねくこととなつた。
また、本陣、庄屋として地域に貢献し、維新に理解したことも無視され、人心は離れてしまう。
主人公・青山半蔵は維新は何だったのか、近代社会とは何かと悶々たる日をおくりつつ、精神に異常を来し、
一族に座敷牢に押し込められてしまう。最後には、座敷牢にて狂死する。
馬篭からの眺望・山中である

中山道・江戸へ八十里・京へ五十二里
中山道は、69宿場からなりたっており、江戸から妻篭宿を過ぎ
馬篭峠(標高800m余り)を超えると馬篭宿である。
同じ中山道11宿の中、奈良井宿は峠を過ぎると平坦な街並みとなるが
馬篭は山中の登り坂で険しい。しかしながら、江戸と京を結ぶ要衝である為に
人と物資の行き来で繁栄を極めたと云う。
ここに、本陣、脇本陣、旅籠や物資集積所があつた。
島崎藤村・「夜明け前」
夜明け前・「木曽路はすべて山の中にある……」
全4冊(岩波文庫)
「藤村記念館」島崎藤村は馬篭に本陣を経営し、庄屋も勤めた
裕福な家庭に育った。
母の実家・島崎家も妻篭宿の本陣を営んでいた。
その後、東京に移り住むが、小説「夜明け前」は、父をモデルにした
とも云われている。
主人公・青山半蔵は裕福な家庭の中で父から国学の素養を学び影響を受ける。
当時の徳川・武士社会に疑念を抱き始め、社会の矛盾に対して平田学派による王政復古の
夢を見る。
幕末の動乱は明治維新となり、変革された世は王政復古で迎えられると確信しつつ、啓蒙を続ける。
しかしながら、明治維新が終われば西洋の近代化の波の中、中山道が廃止され、
新道は木曽川沿いとなり馬篭、妻篭等の宿場街は没落の一途を辿り、貧困社会をまねくこととなつた。
また、本陣、庄屋として地域に貢献し、維新に理解したことも無視され、人心は離れてしまう。
主人公・青山半蔵は維新は何だったのか、近代社会とは何かと悶々たる日をおくりつつ、精神に異常を来し、
一族に座敷牢に押し込められてしまう。最後には、座敷牢にて狂死する。
馬篭からの眺望・山中である